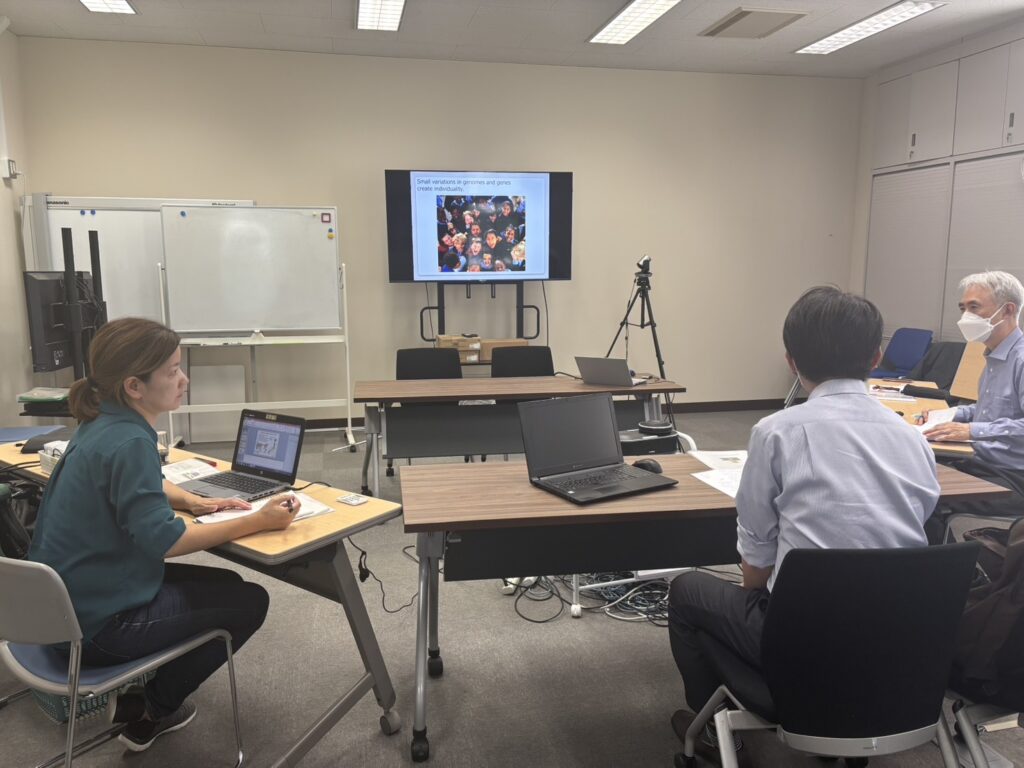英語による講義のための研修② ~英語で効果的に教えるために 模擬授業編~ 参加記 (令和7年9月17日)
今回参加した「英語で効果的に教えるために」の研修では、模擬授業の共有を通じて、授業の導入で学生の関心を引きつけ、学習の動機づけを行い、学習目標を明確にし、問いかけやグループワークで主体的な学びを促す流れを実践的に学ぶことができました。日頃、多くの教員が悩む「学生の集中力の持続」や「多様な学習意欲への対応」といった課題に対し、明日から実践できるような具体的な工夫を、講師の先生はふんだんに解説してくださり、参加者は、すぐにそれらを取り入れ、授業を改善したくなる研修でした。 特に、今回学んだ方法は英語の授業だけでなく、日本語での授業にも応用できる点が大きな収穫でした。 例えば、日本語の講義でも冒頭に「フック」を設け、学生に考えさせる時間を加えることで、受け身の学習から主体的な学びへと転換できることに気づきました。 岡山大学は研究大学として革新的な知を創出し続ける使命を担っていますが、その基盤は、学生が主体的に学び、問いを立て、挑戦できる授業環境にあります。 今回の研修で得た気づきは、将来の研究者を育む教育改善の大きな一歩になると感じています。
(学術研究院共通教育・グローバル領域 教授)
去る9月17日、ダイバーシティ推進課主催で行われた研修「英語で効果的に教えるために」模擬授業編に参加しました。 この研修は、一年前に行われた「英語で効果的に教えるために」という研修の発展版です。英語で講義を行うにあたっての基礎的な知識(語彙や表現の選択、授業の構成の組み立て方など)は一年前の研修で学んでおり、今回は実践編ということで、事前に準備した20分程度の模擬授業を英語で実際にやってみて、相互に批評しあう活動がメインでした。私は普段、英語で授業を行う機会がほとんどないため、日本語の授業スライドを英訳して臨みました。 準備段階ではそれなりに緊張しましたが、受講生が少人数(私を含めてたったの二人)だったこともあり、リラックスした雰囲気の中でたっぷりと時間をとってフィードバックしていただけました。対象として想定したのはどのような学生か(日本人か英語非ネイティブの留学生か、学年は?など)、その上で選んだ語彙が適切だったかどうか、スライドの構成とまとめ方について、さらにはジェスチャーや姿勢などについても、良かった点、改善するとよい点を指摘していただき、非常に勉強になりました。私の模擬授業では、英語非ネイティブの留学生と日本人学生の混合、理学部生物学科の二年生という想定で、なるべく平易な表現を心掛けましたが、口語を多用しすぎると内容の説得力が薄れるという指摘を受け、バランスを取ることの難しさを感じました。
模擬授業以外では、聞き取りやすいスピードについてのトピックが参考になりました。通常は一分あたりの単語数が目安とされますが、専門用語は概して音節数が多いため、授業や学会発表では一分あたりの音節数で考えるとよいそうです。研修では実際に自分の話すスピードを数値化できたので、今後の発表練習に活かしたいと思います。
今回の研修は少人数だったため、非常に贅沢なものとなりました。英語による授業は、どの学部においても今後需要が拡大するものだと思われます。次に同様の研修があれば、多くの先生方にご参加をおすすめしたいです。
(学術研究院環境生命自然科学学域(理) 准教授)